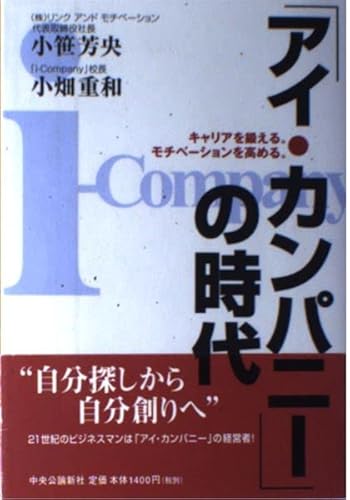キャリアの意思決定は、経営判断だ! – 20代の僕に刺さった1冊
僕が新卒で入社したのは、もうずいぶん前のこと。
当時の会社は社員研修や教育にかなり力を入れていて、メーカーなのに「総合教育研究所」なんていう研修専門子会社まで持っていました(現在はパーソルに事業譲渡されています)。
そんなわけで入社前から「推薦図書」なるビジネス書が5〜6冊送られてきました。
並んでいたのは、当時のビジネス書ランキングに載っているような、いわゆる“王道”なタイトルばかり。
本好きの親父が「意外とミーハーだなあ(笑)」と評していたのを、今でも覚えています。
真面目だった僕は、きちんと全冊読みました。
でも、正直、そのほとんどの本はタイトルも内容も覚えていません。
父が言った通り、流行りもの中心で、あまり本質に踏み込んだ本ではなかったのかもしれません。
ですが!
そんな中でも、1冊だけ今もはっきり覚えている本があります。
それがこちら👇
2003年出版なので、けっこう古い本なのですが『自分自身を「自分株式会社の社長」と捉えて、勤め先に依存しないキャリアを歩む』というのが主眼。
細かな内容はさすがに覚えていないのだけれども、当時強く印象に残ったポイントが2つ(20年前の記憶なのでちょっとあやふやですが…😅)。
ポイント1:自分を経営者として捉えよ
自分自身を「株式会社」として見立てるならば、自分株式会社(アイ・カンパニー)の社長として、自分自身のキャリアについて「経営的な意思決定」ができる!
ポイント2:勤め先に依存するな
勤め先は、あくまでも「クライアント」。長期的なパートナーシップを育むことは良いが、勤め先に依存するようなキャリア形成は人生リスクが高い!
ポイント1: 自分を経営者として捉えよ
経営者であれば、社員にビジョンを示し、売上を伸ばし、コストを抑え、将来に向けた投資も計画的に行う必要がありますよね。
いわゆる経営の意思決定なのですが、会社経営の意思決定は👇のように個人にも当てはまるよ〜という風に当時は理解しました。
- 会社の将来ビジョン・中期戦略→ 人生目標・キャリアゴール
- 売上成長 → 年収アップ
- コスト削減 → 無駄遣いの最小化
- 将来投資 → 資格取得・勉強・人脈作りなどの種まき
会社というものがどういう物か分からなかった当時の僕でも、考え方は分かりやすく、本を読みながら入社後3年間で達成したいことを漠然と想像したことを覚えています。
その時にイメージして実際に実現したのが、会社の留学支援制度を使った「海外大学院への社費留学」。
とりあえず「入社4年目で社費留学する」というざっくりとした目標を立てて、そこから逆算して、大まかなTo Doリストを作ったんです。
ただ入社して蓋を開けたら、入社6年目以降でないと留学制度に応募できないというルールが判明。いきなり目標が崩れちゃうのですが・・・。
ところが、上司に恵まれた&ラッキーな事情が重なり、なんと入社5年で留学させてもらえることに!
当時としては異例の出来事だったので、社内でも最短に近かったのかもしれません。
ラッキーな事が起きたおかげというのもありますが、目標から逆算した To Do リストを消化し、少しずつ準備していたからこそ、チャンス到来時の波に乗れたんだなぁと、今になってしみじみ感じています。
ポイント2: 勤め先に依存するな
副業解禁、パラレルキャリア、リカレント教育など、よくニュースなどで耳にすることが多くなりました。
僕が新入社員だった時は、そういうキーワードが登場する前だったので、これからサラリーマンになろうとする僕には「勤め先に依存するな」というメッセージのインパクトはかなり強かったです。
リストラとは、いわば「最大のクライアントから契約を打ち切られる」ことに他なりません。
自分自身の経営者として、そのリスク対策はできているのか?というような趣旨を問いかけていたのだと思います。
具体的な例を言うと「社内人脈はリストラされてしまうと価値がなくなりやすい。だから社外にも人脈を作っておきなさい」といった事例です。
結果的に僕が選んだ対策は、本業以外の複業に携わるという方法。
以前、👇の記事で紹介した起業家育成の団体運営もやりましたし、現在も本業の精子バンク以外にグロービス経営大学院のコーポレート・ファイナンスの授業を受け持っています。
リモートワークが当たり前になり、ノマドワーカーであったり、複数の肩書きで働いたりすることが珍しくなくなった今、『自分自身を経営する』というアイ・カンパニーの考え方は、むしろ“今こそ”リアルに響く内容。
特に20代の皆さんは、最初の職場がフルリモートだったり、数年で転職したり、SNSで複業の機会を得たりと、キャリアの選択肢がとても多い世代だと思います。
そんな時代だからこそ、「自分株式会社をどう経営するか?」という視点は、昔よりも必要になっている気がします。
***
新たに付け加えたいポイント
『「アイ・カンパニー」の時代』を読んでからすでに20年。
内容は薄れていない(少なくとも20代の方には)と思うのですが、もし僕が加筆を許されるとしたら家族やパートナーのこと。
新入社員の時は、I (私) のことを考えていればいいので、アイ・カンパニーで良いのですが、パートナーができ、家族ができると、We (私達)という世帯単位での経営にシフトする必要があると思うのです。
複数の事業を営んでいる会社の場合、異なる事業を掛け合わせることでシナジー(相乗効果)を出すことが重要なのですが、同じ考え方が世帯でも適用できるという発想です。
例えば共働きの場合、それぞれが収入を持っていますが、それぞれを別個に考えるのではなく、世帯全体として収入を高めたり、世帯としてのクオリティ・オブ・ライフ(QOL)を高めるためにはどうするのか?という統合的な意思決定を二人で議論できているかと言う事です。
いわば「取締役が二人いる」状態。
わが家の場合、「フリーランスだった妻がデンマークの大学院に留学する」という決断が、世帯としてのクオリティ・オブ・ライフを大きく変える転機になりました。
そういう意味では、株式会社自分自身は株式会社私達「ウィ・カンパニー」として、発展していくのが自然なのかなぁと思ったりもします。
これから『「アイ・カンパニー」の時代』を読まれる方は、ぜひパートナーや家族と一読されることをお勧めします。
***
さて、Amazonのレビューを見ていたら、「35歳ぐらいまでの方でサラリーマンの方、この本を手に取るチャンスがあったことは幸せですね」というコメントを見つけました。
まさに、Yes!!
思わず頷いてしまいました!
正直言うと、奥さんと一緒に暮らしているデンマークのクオリティ・オブ・ライフはかなり高め。
それは「幸せの国ランキング2位の国」に住んでいるからというわけではなく、奥さんと一緒に築いてきたキャリアや経験、人とのつながりがあるからだと思っています。
振り返ると『「アイ・カンパニー」の時代』を読んで感じたエッセンスが意思決定の根底にあり、現在に繋がっているような気がします。
だからこそ、これからキャリアを築いていく20代の方には、ぜひ一度手に取ってほしい一冊です。
***
そうそう、今日の見出し画像は、オーフス市内にある Bog og Vincafe というカフェ兼ワインバー。実は本屋さんが経営しているので、本を手に取りながら、ワインやコーヒーが飲めちゃうシャレオツ空間です。